【卒業生インタビュー】研究を“社会”に実装する ― GIAで気付いた“現場”の大切さ(株式会社Emeraid 島 碧斗氏 インタビュー)
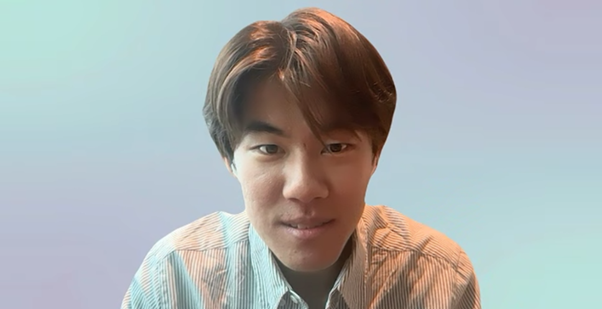
Green Innovator Academy(以下GIA)は、「未来を自らより良く変えていこうとするイノベーターの育成」を目的に、2021年に開講しました。これまでに企業の経営幹部候補や若手リーダー、ベンチャー企業のCEO、省庁・自治体職員、学生など、2025年3月時点で400名を超える卒業生を輩出、社会の幅広い分野で活躍されています。
今回は第1期(2021年度)の学生プログラムに参加され、その後に株式会社Emeraidを立ち上げられた島碧斗氏にお話ををうかがいました。
PROFILE
島 碧斗(Shima Rikuto)氏
株式会社Emeraid 代表取締役CEO (Chief Executive Officer)
東京大学大学院 工学系研究科 化学生命工学専攻
分子生物学を専門とし、RNAに関連する病態解明の研究を行う。高校1年次より医療課題解決事業に取り組み、以後、精神疾患・フレイル・心不全などの疾患に対して課題解決アイデアを考案。日本製薬工業協会との共同プロジェクトのリーダーを務めた。ライフサイエンス領域でのベンチャー・キャピタルファンドにおいて、リサーチ・アシスタントとしての従事経験を有する。JSBi認定 バイオインフォマティクス技術者。
― GIA卒業後東京大学大学院で研究を行う傍ら、会社を立ち上げられたとのことですが、現在の研究と仕事について教えてください。
東京大学大学院でRNA修飾に関する研究を行っています。動物の体では、DNAからRNAに遺伝情報が「転写」され、RNAの情報をもとにタンパク質が合成されます。この過程の中で、RNAが官能基の付加・置換・変換などを受けて新たな形となる化学的な「修飾」が行われるのですが、これが異常を起こすと重大な病を引き起こすことにつながってしまいます。RNA修飾異常のメカニズムを知ることで、現在治療法が確立されていない疾患の根治治療法の創出につなげたいと考えています。
一方の仕事としては、ヘルスケア×AIというテーマで事業を行っています。大学病院や製薬企業と協業しながら、創薬時の治験を進めていく際に人力に頼っていた部分をAIで効率化するなど、最先端の技術を導入することで医療問題の解決を試みています。
― 高校生の頃から医療に興味があったそうですね。その中でGXに特化したGIAに参加したきっかけについて教えてください。
いま振り返ると、当時は学部1年生でいろいろな事象に興味が分散していたというところはあったと思います。ただ、ずっと前から生命・有機物などの「動きの予想ができないもの」に対する強い興味がありました。この軸をミクロで突き詰めていけば、いま行っている細胞や遺伝子の研究につながる一方で、マクロの観点で見ると「自然」に繋がるのではないかとも考えていました。人の体の中で起きている現象と同じように自然も複雑な要素が絡み合い、人智を超えた規則性の中で成り立っているように感じていて、それに向き合いたいと思っていたところで、たまたまGIAを見つけたのが参加のきっかけです。
― 有機的な動きの予想ができないものとして、自然と遺伝子にある種の共通項を見出していたとのことですが、実際にGIAに参加してみて両者の類似性は感じましたか。
正直なかったです。笑
自分が都会にいて純粋な意味での自然を見切れていないという側面もあると思いますが、人間という外部要因が多大に介在している自然と、人の中のミクロな現象は全く別物に見えました。
一見似たものに見えたものが実は違ったという気付きもとても面白かったです。
― そのような中で、GIAで得たものや印象に残っていることを教えてください。
一番印象に残っているのは、福島のフィールドワークです。実際に現場を見ることや、実際にその場にいる人から話を伺うことの重要性を学ぶことができました。
グループワークでは政策提言に取り組みました。ただ、当時はなかなかうまく進められずに苦労しましたし、最後に心から納得のいくものが作れたという感触もありませんでした。課題自体がそもそも難しかったというのもありますが、現場の本当の課題を知らなかったからというところも理由の一つだと思います。先ほどの福島フィールドワークの話にもありましたが、現地や現物を知ることの大切さを感じました。
GIAの講義やグループワーク、フィールドワークはもちろんですが、参加者のコミュニティに価値を感じています。GIA卒業後は頻繁にメンバーに会うわけではないですが、たまに会って意見交換したり、facebook等の媒体でみんなの活躍を見るとすごく刺激になります。1期生は年齢や学部も違う学生が100人、さまざまなセクター出身の社会人50人の計150人近くが集まっていてある種の「カオス」だったと思いますが、その分、普段出会えない属性の人が多く、自分のことを一歩引いて見ることもできたのも良い経験でした。
― 起業後どのような思いを持って事業に取り組まれているのでしょうか。
もちろん事業体としてお金を稼ぐ必要はありますが、純粋に収益を得ることを目的としたビジネスライクの側面よりも、一見すると収益は出にくいかもしれないけれども社会的にニーズがありそうな研究開発を会社主導でやりたいという思いがあります。その結果として、自分の目標でもある新たな治療法の確立であったり、より多くの人の命を救うというところにつなげていきたいです。収益性の高い事業会社というよりも民間の研究機関を目指しているイメージです。
― 最後に今後の展望について。会社として、また個人としての、ふたつの側面から教えてください。
会社としては、より機械学習に近い専門性の高い人を巻き込んでいきたいという思いがあります。自分のようなヘルスケアやバイオロジーをバックグラウンドに持つ人間と、AIに特化した人たちが一緒に働くことで生まれる画期的な技術を、実際の現場に入れるとどうなるかを検証していきたいです。2024年にタンパク質の構造を予測するAIモデルAlphaFold2がノーベル化学賞に選ばれましたが、これは大学主導ではなくGoogle DeepMindが開発したものなんですよね。自分たちもこの例のように機械学習の専門性を持った人が集い、その技術をもとに専門的(ヘルスケア)な新しい技術を作る機関になれたらと思っています。
個人として、最終的に自分がやりたいことは「従来なかった画期的な新薬・治療法を見つけること」です。その中で自分の役割は、研究者として色々なシーズを探していくことにあるのかなと思っています。一方で、そのシーズに対する解決案を世に出していく部分に関しては、Emeraidのような箱を作っていくことで関わっていければと思っています。今後は自分自身の専門的な研究と箱として作っている事業体が合流することで、最短ルートで自分自身のやりたいことを実現したいです。
― 本日は貴重なお話をありがとうございました!
<インタビュー後記>
研究者と会社CEOの2つの顔を持った島さん。GIA受講当時のことを懐かしみながら、いまの研究・事業について前向きかつ楽しそうにお話されていた姿が印象的でした。知的好奇心の赴くままに突き進む島さんに、こちらも強い刺激を受けた1時間でした。
今後も多様な卒業生のインタビューを掲載していきますのでご期待ください。